結露対策のアイデア9選!予防の習慣やすぐにできる対処法
更新日:
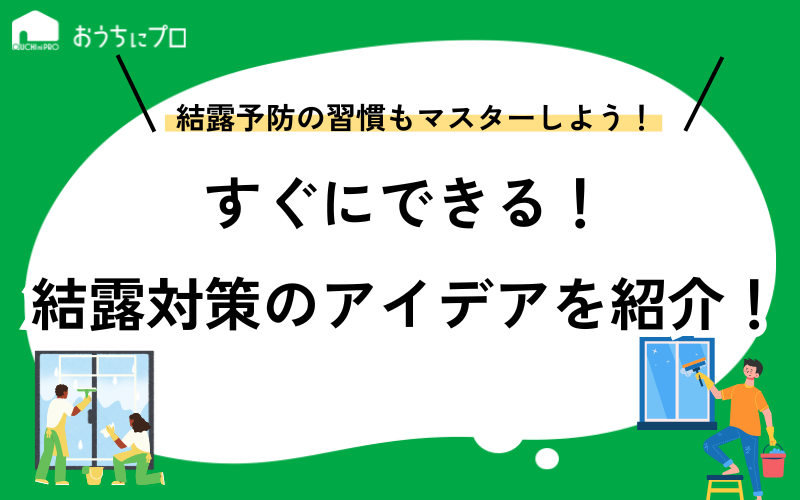
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する「結露ができて窓がびっしょり濡れている」「結露が発生しないようにしたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
結露を放置すると、室内にカビが生えたり壁やサッシが傷む可能性があるため、定期的な換気や結露防止グッズの使用、室温や湿度の調整などを行って結露対策をする必要があります。
本記事では、結露対策のアイデア9選と日常生活から見直す結露防止の習慣、万が一結露ができた際の対処法などを詳しく解説します。
結露が生じやすく対策が欠かせない6つの場所も紹介しているので、今すぐ結露をどうにかしたい方はぜひ参考にしてみてください。
- この記事でわかること
-
- ・結露や窓ガラスやサッシのほか、クローゼットや家具の裏側、観葉植物を置いている部屋などにも生じやすい
- ・結露対策は定期的な換気・空気の循環・湿度40~60%程度や室温20度程度の維持・暖房器具はエアコンや電気ストーブを使うことなどが大切
- ・家具を壁から離して設置・加湿器を部屋の中央付近に設置・入浴後や調理中の十分な換気など、日々の習慣の見直しも重要
- ・結露を放置すると、カビが生えたりサッシや壁が傷んだりする可能性がある
- ・万が一結露が生じた場合はすぐに水滴を拭き取り、カビ予防としてアルコール除菌スプレーを吹きかけることが大切
- ・戸建て以外に、気密性が高いマンションやアパートでも結露対策を行う方がよい
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!目次
- 【記事作成】おうちにプロ 編集部
- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!
窓の結露はなぜできる?
結露とは、空気中の水蒸気が水滴となって表面に現れる現象を指します。
冷たい飲み物を入れたコップの外側に水滴がつくのと同じ原理で、たとえば冬の朝に窓ガラスが濡れているのが結露です。
窓に結露がつきやすいのは、外の冷気でガラスの表面が冷え切っているためです。
冷え切ったガラスの表面に室内の湿った空気が触れると、空気が抱えきれる以上の水分が行き場を失い、水滴として付着します。
空気は、温度によって含める水蒸気の量が変わるという特徴があります。暖かい空気ほど多くの水分を抱え込めますが、温度が下がると一気に限界値が小さくなります。
この限界値のことを「飽和水蒸気量」と呼び、超えてしまった分が水滴となるのです。
結露が生じやすい6つの場所
家の中でも特に結露が生じやすい場所は、主に次の6つです。
-
窓ガラスやサッシ
-
観葉植物を置いている部屋
-
クローゼット
-
家具の裏側
-
浴室の天井
-
キッチンの天井
まず代表的なのが窓ガラスやサッシです。窓周辺は外気に面していて冷たくなりやすいため、室内の湿気が触れて水滴がつきやすくなります。
観葉植物を置いた部屋も要注意で、植物は水分を蒸散させるため湿度が上がりやすくなります。
また、浴室の天井も湿気が溜まりやすい場所です。入浴後の蒸気が天井に上がり、冷えた部分に水滴となって残ります。
さらに、料理の湯気が充満しやすいキッチンの天井も結露の発生ポイントです。
特に冬場は天井付近が外気で冷えて、油分を含んだ水滴が付着することで汚れも広がりやすくなる点に注意しましょう。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!今すぐできる!結露対策のアイデア9選
「結露対策は大変そう」と思う方もいるかもしれませんが、次の9つの方法であれば今すぐ手軽に試せます。
結露対策の9つの方法
①定期的に換気する
②サーキュレーターや扇風機で空気を循環させる
③湿度を40~60%程度を維持する
④室温は20度程度を維持する
⑤洗濯物は室内ではなく浴室に干す
⑥観葉植物は窓際以外に置く
⑦暖房器具はエアコンや電気ストーブを使う
⑧窓用ヒーターを使う
⑨結露防止グッズを使う
①定期的に換気する
結露を防ぐうえで欠かせないのが換気です。室内の空気が動かずこもった状態になると湿度が上がりやすくなり、窓ガラスや壁に水滴がつきやすくなります。
そのため、換気で外気を取り込みながら湿気を逃がすことで、結露の原因となる室内と窓との温度差を小さく保つことが可能です。
しかし、効果的に換気を行うにはただ窓を少し開けるだけでは不十分です。
冬場は冷気が入ってくるため窓を閉め切りがちですが、最低でも1時間に1回程度は換気するのが理想です。
特に調理や入浴のあとは室内の湿気が急増するため、しっかりと換気しておくと結露を大幅に減らす効果が期待できます。
空気の入れ替えを短時間で行えば、室温が大きく下がることもありません。
②サーキュレーターや扇風機で空気を循環させる
結露を減らすためには、部屋の空気をよどませないことが大切です。
湿った空気が1箇所に溜まると、その部分の温度が下がったときに水滴ができやすくなります。
そこで、サーキュレーターや扇風機を使って空気を循環させることで、部屋全体に温度と湿度を均一に行き渡らせることができ、結露の発生を抑えられます。
また、天井付近に溜まりやすい暖かい空気を床に向かって送るようにすれば、足元の冷えも和らぎ快適に過ごせます。
サーキュレーターは空気を直線的に遠くまで運ぶのが得意で、窓周辺や部屋の隅まで風を届けやすいのが特徴です。
扇風機でも同じように使えますが、より広範囲をカバーしたい場合はサーキュレーターの方が効率的といえるでしょう。
③湿度を40~60%程度を維持する
結露を防ぐうえで大切なのが、室内の湿度管理です。湿度が高すぎると、空気に含まれる水蒸気の量が限界を超えやすくなり、冷えた窓に水滴として現れてしまいます。
逆に湿度が低すぎると、今度は喉や肌の乾燥を招くため、健康や快適さに悪影響を及ぼします。
そのため、一般的に快適とされている湿度40~60%の範囲を保つようにしましょう。
一方で、湿気がこもりやすい部屋では除湿機の活用が有効です。
特に窓際や北側の部屋は結露が発生しやすいため、除湿機を置くと湿度の上昇を抑えられます。
④室温は20度程度を維持する
結露を防ぐには、室内の温度管理も重要です。室内と外気の温度差が大きいほど、窓や壁に結露が発生しやすくなります。
特に暖房器具で部屋を必要以上に高温にすると、冷たい窓ガラスとの温度差が大きくなり、水滴がつきやすくなるため注意が必要です。
そのため、室温は無理に高くせず、20度前後に保つのがよいとされています。
また、暖房器具を使う際は、室内全体の温度が均一になるよう工夫するとさらに効果的です。
暖かい空気は上に溜まりやすいため、サーキュレーターや扇風機で空気を循環させると、足元まで暖かさが行き渡り窓付近の冷えも軽減されます。
⑤洗濯物は室内ではなく浴室に干す
室内で洗濯物を干すと、部屋の湿度が急激に上がって結露が発生しやすくなります。
特にリビングや寝室の窓際に干すと、窓ガラスやサッシに水滴がつきやすくなるため、結露を防ぎたい場合は避けた方が無難です。
そこで洗濯物を浴室に干すと、湿気がこもったとしても換気扇や窓から効率的に外に排出されるため、室内全体の湿度上昇を抑えられます。
もし浴室の換気扇が弱い場合や浴室乾燥機がない場合は、扇風機やサーキュレーターで浴室内に風を送るだけでも、乾燥を早めて結露の発生を軽減できます。
このように、洗濯物の干し場所を工夫するだけでも結露の発生を大幅に抑えることが可能です。
⑥観葉植物は窓際以外に置く
室内に観葉植物を置いている方も多いかもしれませんが、植物は空気中に水分を放出するため、室内の湿度を高める可能性があります。
特に窓際に観葉植物を置いていると、冷たい窓ガラスに湿気が集中しやすくなり結露の原因となります。
窓周辺で結露が繰り返されると、カビや汚れが発生しやすくなるため注意が必要です。
複数の観葉植物をまとめて置く場合は、間隔をあけて風通しを確保すると効果的です。
また、水やりの方法も結露対策に影響します。
過剰な水やりで土が過湿状態になると蒸発する水分が増えるため、水やりは控えめにして土の表面が乾いたタイミングで行うのがよいでしょう。
⑦暖房器具はエアコンや電気ストーブを使う
結露を抑えるためには、暖房器具の種類にも注意が必要です。
石油ストーブやガスストーブは燃焼する際に水蒸気を発生させるため、部屋の温度が上がるだけでなく湿度も上昇しやすくなります。
湿度が高くなると窓や壁に水滴がつきやすくなるので、結露対策を行いたい場合は使用を控えた方がよいでしょう。
室温を快適に保ちながら、室内の湿度を過剰に上げることなく使用できるため、冬場の結露対策として適しています。
使い方のポイントとしては、部屋全体に暖かい空気が行き渡るように配置することです。
たとえばエアコンの風向きを工夫したり、サーキュレーターで空気を循環させたりすると、窓周りの冷たい空気と暖かい空気の差を縮められて、結露の発生をさらに抑えられます。
⑧窓用ヒーターを使う
窓の表面が冷えると結露が発生しやすくなるため、窓用ヒーターを活用することでガラスの表面を暖かく保ち、室内との温度差を減らせます。
窓用ヒーターは設置が簡単で、既存の窓に差し込むタイプや、窓の下に置くタイプなどがあります。
ガラスの温度が上がると結露ができにくくなるだけではなく、室内の空気も冷えにくくなり、冬場でも快適に過ごせる点がメリットです。
一部だけが暖かいと、冷たい部分に結露が残る可能性があります。
また、ヒーターを長時間つけっぱなしにするのではなく、湿度や外気温に合わせて調整すると効率的です。
⑨結露防止グッズを使う
結露対策は、結露防止グッズを使うと簡単に行えます。たとえば、次の5つの道具があると便利です。
| アイテム名 | 特徴 |
|---|---|
| 結露防止スプレー | 結露の発生を抑えるスプレーで、吹きかけて乾拭きするだけで使用可能 |
| 結露吸水シート | 窓に直接貼れるシートで、簡単に装着可能 |
| 結露吸水テープ | 窓の下に貼るだけで水滴を吸収し、サッシや巾木の損傷を防ぐ便利アイテム |
| 結露取りワイパー | 持ち手に水を溜められるタンク付きのワイパーで、下から上に動かすだけで水滴を回収可能 |
| 断熱シート | 窓の冷気を遮断することで結露を防止可能 |
たとえば、断熱シートは窓ガラスの表面温度を下げない役割を持ち、結露自体の発生を抑える効果が期待できます。
一方で結露吸水テープや結露取りワイパーは、すでに発生した水滴を効率よく回収し、壁や家具へのダメージを防ぐための実用的な道具です。
特に結露防止スプレーは手軽に使えるアイテムで、シュッと吹きかけて乾拭きするだけで結露を防げます。
それぞれのアイテムを単品で使うのではなく、組み合わせて使用すると、結露の発生を防ぎつつ掃除やメンテナンスの手間も減らせます。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!日常生活から見直す結露防止の習慣
ここまで紹介したように簡単にできる結露対策もありますが、長期的な効果を求める場合は日常生活を見直して、結露が発生しづらい環境を整えることが大切です。
具体的には、次の3つを意識してみてください。
結露防止の生活習慣
・家具を壁から離して配置する
・加湿器を結露しにくい場所に設置する
・湿気がこもりやすい入浴後や調理中は十分換気する
家具を壁から離して配置する
家具を壁にぴったりとつけて配置すると、背面に空気の通り道がなくなり湿気がこもりやすくなります。
特に、外気に接する外壁側の壁は温度が下がりやすいため、家具の裏に湿気が溜まると結露が発生して、カビやダニの温床になるリスクが高まります。
そのため、家具と壁の間には5〜10cm程度の隙間を空けて、空気が循環できる状態を作ることが重要です。
隙間を設けることで壁との温度差による結露が発生しにくくなり、湿気を上手に逃がすことができます。
また、隙間を空けて空気の流れを妨げないことで、暖房の効率も上がって部屋全体の快適さも向上しやすくなります。
加湿器を結露しにくい場所に設置する
冬場は乾燥対策のために加湿器を利用する家庭も多いですが、設置場所によっては結露の原因になることがあります。
特に窓際や壁際に加湿器を置くと、発生した水蒸気が冷たい面に集中して結露が一気に進んでしまうおそれがあるため、加湿器は部屋の中央付近に設置するのが理想です。
高い位置に置くことで床に直接置くよりも水蒸気の拡散性が高まり、空気全体に水分が行き渡りやすくなります。
また、窓や外壁からはできるだけ離すことで、冷たい面のみに湿気が集中せず結露を軽減できます。
さらに、湿度の管理機能が付いた加湿器を選ぶことも大切なポイントです。
湿気がこもりやすい入浴後や調理中は十分換気する
結露の大きな原因のひとつが、生活の中で発生する水蒸気です。
特に入浴後の浴室や調理中のキッチンは多くの水蒸気が発生し、換気が不十分であれば室内に湿気がこもって結露が発生しやすくなります。
キッチンでは、調理中に必ず換気扇を使用しましょう。特に煮込み料理や蒸し料理は水蒸気の発生量が多いことがあり、換気を怠るとリビングやダイニングに湿気が広がって結露の発生リスクが高まります。
調理が終わったあとも、しばらくは換気扇を回し続けると安心です。
窓の結露を放置するとどうなる?
何も対策をせず、窓の結露を放置すると次のようなリスクがあります。
窓の結露を放置するリスク
・カビが生える
・サッシや壁が傷む
カビが生える
結露をそのままにしておくと、窓ガラスやサッシが常に濡れた状態になり、カビが発生しやすくなります。
特に窓の下部やゴムパッキン、サッシの隅は湿気が溜まりやすく、カビが繁殖しやすい場所です。
一度カビが生えると、見た目が悪くなるだけではなく掃除をしても跡が残りやすく、完全に除去するのが難しくなります。
また、窓まわりに生えたカビは壁紙やカーテン、木材部分などにも移り、気づいたときには被害が広がっているケースも珍しくありません。
日常的な結露対策とこまめな水分の拭き取りを怠ると、最悪の場合はカビが広範囲に繁殖して取り返しのつかない状態になる可能性もあるでしょう。
サッシや壁が傷む
窓ガラスの結露で発生した水滴は下へ流れ落ちて、サッシの隙間や窓枠、壁の表面などに染み込みやすくなります。
アルミや樹脂でできたサッシでも、長期間濡れたまま放置すると腐食や劣化が進んでしまい、動きが悪くなることがあります。
壁紙の剥がれやシミは初期症状にすぎず、結露を長期間放置すると建材の劣化を進めて、住宅全体の耐久性を低下させてしまいます。
特に木造住宅では湿気によって木材が傷むことで、家そのものの寿命を縮めるリスクもあります。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!迅速な対応が大切!結露ができた際の対処法
万が一結露が生じた場合は、すぐに次の2つの対処法を実践しましょう。
結露ができた時の対処法
・水滴を拭き取る
・除菌スプレーをかける
水滴を拭き取る
結露に気づいた場合、すぐに水滴を拭き取ることが大切です。
窓ガラスやサッシに残った水分を放置すると、下へ流れて溜まってしまいサッシの隙間や壁紙に染み込みやすくなります。
その結果、カビが繁殖したりシミができたりする原因となり、住宅の劣化を早めてしまうのです。
雑巾やマイクロファイバークロスなどを使い、しっかりと水分を吸い取るように拭くと効果的です。
また、窓専用の結露取りワイパーを使えば、短時間で水滴を集められるため忙しい朝でも時間をかけずに掃除できます。
除菌スプレーをかける
結露を拭き取ったあとは、アルコールを含む除菌スプレーを活用することで、カビの繁殖を抑えることができます。
カビの胞子は目に見えないうちに広がってしまい、結露による湿気が残っていると一気に繁殖する危険性があります。
そこでカビの弱点であるアルコール除菌スプレーを吹きかけると、表面に残った胞子の活動を抑制できるためカビ対策に有効です。
特に、ゴムパッキンやサッシの隅などはカビが発生しやすい部分であるため、重点的にスプレーしておくと安心です。
また、カーテンが窓に触れている場合は湿気が移ってカビが生えることもあるため、カーテンの裾にも軽くスプレーしておくと予防効果が高まります。
結露対策に関するよくある質問
結露が広範囲に発生して毎日の拭き取りが追いつかない場合、まずは湿度の管理を徹底することが大切です。加湿器の使用を控えるか、湿度設定を40〜60%に調整しましょう。また、窓に断熱シートを貼ったり窓用ヒーターを設置したりすると、窓ガラスの表面温度が上がり結露が軽減されます。さらに、換気の頻度を増やすことも有効です。24時間換気システムがある場合は必ず稼働させて、ない場合はこまめに窓を開けて空気を入れ替えましょう。結露がひどいまま放置するとカビや住宅の劣化などにつながるため、日々の対策に加えて環境全体を見直すことが欠かせません。
マンションでも、必ず結露対策を行いましょう。戸建てに比べると、マンションは気密性が高い構造なため、外気との温度差が大きくなりやすく、特に冬場は窓ガラスやサッシに大量の結露が発生します。放置するとカビやダニの発生を招き、健康被害やアレルギーの原因になる可能性もあります。また、サッシや壁紙が傷んでしまうと資産価値の低下にもつながりかねません。特に北向きの部屋や日当たりの悪い場所は湿気がこもりやすいため、結露防止シートやスプレーの利用、家具を壁から離して配置する工夫など、賃貸でも実践できる手軽な方法を取り入れることがおすすめです。
賃貸住宅の場合、独断で壁や窓に大きな工事を加えることはできませんが、日常的な工夫で結露は大幅に抑えられます。たとえば、窓ガラスに貼る結露防止シートや断熱フィルムは賃貸でも利用可能で、剥がしたあとに跡が残らないタイプを選べば安心です。また、窓の下部に吸水テープを貼っておくと、水がサッシに溜まることを防げます。ほかにも加湿器の位置を工夫したり、換気扇をこまめに回したりといった生活習慣の改善も有効です。家具を壁から数cm程度離すだけでも空気の通り道ができ、結露によるカビの発生リスクを減らせるでしょう。まずは、費用をかけずにできる小さな工夫から始めてみましょう。
もし結露を放置してカビが発生してしまった場合は、できるだけ早く取り除くことが大切です。軽度のカビなら中性洗剤や消毒用エタノールを吹きかけて数分程度置き、そのあとlに濡れた布で拭き取れば落としやすくなります。なかなか落ちない頑固なカビには、塩素系のカビ取り剤を使う方法が有効です。水で湿らせたキッチンペーパーをカビが生えている部分に貼り付けて、その上からスプレーして20分ほど置くと、薬剤が奥まで浸透してカビを落とす効果がより高まります。そのあとは、乾いたペーパーで薬剤をしっかりと拭き取りましょう。作業時は必ず換気を行い、ゴム手袋を着用して安全に掃除することが大切です。再発防止のためには、掃除後に除菌スプレーを吹きかけて、日常的に結露を拭き取る習慣を身につけることが欠かせません。
二重窓や内窓は、結露対策として有効な方法のひとつです。窓ガラスが一枚だけの場合、外の冷たい空気が直接伝わりやすく、室内との温度差によってガラス表面が冷えて結露が発生しやすくなります。しかし、二重窓や内窓はガラスとガラスの間に空気層を作り出し、断熱効果を高める仕組みです。空気層が冷気の侵入を防ぎ、窓表面の温度が下がりにくくなるため、結露の発生が抑えられます。また、冷暖房効率の向上や防音性の向上といったメリットも期待できます。二重窓や内窓を取り入れるには初期費用がかかりますが、長期的に住環境を快適に保ちたい方にとってはおすすめの対策といえるでしょう。
適切な結露対策で室内環境を守ろう
窓やサッシに水滴がつく結露は、放置してしまうとカビやダニの発生につながり、健康被害や住まいの劣化を招く原因になります。
特に木造住宅では、壁や床材が傷んで建物自体の寿命を縮めるおそれもあるため、日ごろからの対策が欠かせません。
結露を防ぐためには、室内の湿度管理やこまめな換気、家具の配置の工夫といった生活習慣の見直しが効果的です。さらに、窓用ヒーターや断熱シート、結露吸水グッズなど、市販の便利アイテムを活用することで手軽に改善できます。
さらに、結露が発生してしまった際には、水滴をすぐに拭き取って除菌スプレーで清潔に保つことが重要です。
毎日のちょっとした工夫を積み重ねることで、快適で清潔な住環境を守り続けることができます。
| 地域 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。
※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。
※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する










