壁紙の汚れ落としの方法!必要な洗剤や壁紙ごとの掃除方法の違いを紹介
更新日:
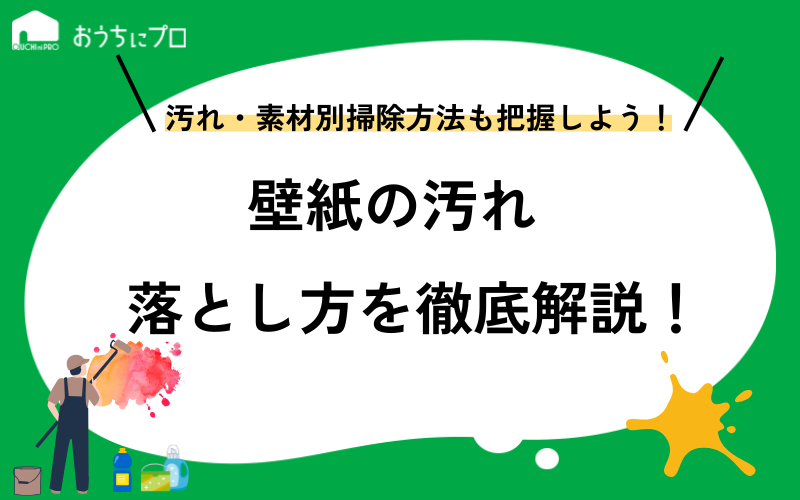
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する「壁紙が汚くて困っている」「簡単に汚れを落としたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
壁紙の汚れを落とすと部屋の印象がガラッと変わるため、中性洗剤やアルカリ性洗剤などを活用しながらきれいに汚れを落としましょう。
本記事では、汚れの種類別に壁紙の汚れ落としの方法や、掃除に必要な洗剤やアイテムなどを詳しく解説します。
壁の素材ごとの掃除方法の違いや、掃除後の壁の汚れを防ぐ方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- この記事でわかること
-
- ・壁紙の汚れ落としをすると、部屋がぐっと明るく清潔な印象になる
- ・自宅の壁紙は手垢やホコリ、油汚れやクレヨン、カビやタバコのヤニ汚れなどで不衛生な状態になる
- ・掃除には中性洗剤やアルカリ性洗剤などを使用し、汚れの種類ごとに使い分けることが大切
- ・手垢・油汚れ・クレヨンやペンの汚れなどには「中性洗剤」、こびりついた油汚れ・タバコのヤニ汚れには「アルカリ性洗剤」がおすすめ
- ・どうしても汚れが落ちない場合は、プロによるハウスクリーニングが有効
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!目次
- 【記事作成】おうちにプロ 編集部
- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!
壁紙の汚れを落とすと印象がガラッと変わる
壁紙の汚れは、放置しておくと部屋全体の印象を暗くしてしまう原因になります。
ちょっとした手垢や食べこぼし、子どもの落書きなど、日常生活で付着する軽い汚れでも、室内の印象に大きな影響を与えます。
壁紙の汚れを適切に落とすことで、部屋がぐっと明るく清潔な印象になります。
特に白や淡い色の壁紙は汚れが目立ちやすいため、定期的なお手入れが欠かせません。
ビニールクロスのような水拭き可能な壁紙は、水で濡らした柔らかい布やスポンジで軽くこすれば汚れを落とせます。
一方で、紙や布の壁紙は水分に弱いため、乾いた布を使った乾拭きでの掃除が適しています。
定期的に壁紙をチェックして、汚れを見つけたら早めに対処することで、部屋の印象を常に清潔にすることが可能です。
壁紙が汚れる原因は?
壁紙は、次のような原因によって汚れやすくなります。
壁紙の汚れの原因
・ホコリ
・油汚れ
・手垢
・クレヨンやペン
・カビ
・タバコ
ホコリ
壁紙に付着するホコリは、日常生活で発生しやすい一般的な汚れのひとつです。
特に、高い位置や家具の裏、あまり掃除しない隙間の壁などは、空気中に浮遊するホコリが積もりやすく、黒ずみとして目立つことがあります。
また、ホコリはほかの汚れと結合しやすく、手垢や油汚れと混ざると簡単には落ちなくなります。そのため、壁紙を清潔に保つためにはこまめな掃除が大切です。
雑巾やハンディモップを使って壁の表面のホコリを取り除くことで、汚れが壁に定着するのを防げます。
リビングや子ども部屋、通路などの人の出入りが多い場所は特にホコリが溜まりやすいため、定期的に拭き掃除を行うと壁紙の美しさを長く保つことが可能です。
油汚れ
壁紙に付着する油汚れは、主にキッチン周辺で発生します。
調理中に飛び散った油や揚げ物の油煙、調味料の飛び散りなどが原因で、壁紙に黄色のベタつきが残ることがあります。
油は冷えると固まりやすく、放置すると頑固な汚れとして定着して、通常の拭き掃除では落としにくくなるため注意が必要です。
また、油汚れはホコリや手垢と混ざると、より目立つ黒ずみやしつこい汚れになりやすい特徴があります。
対策としては、調理後にすぐに湿った布や中性洗剤を使って軽く拭くことが効果的です。
定期的に壁を掃除することで、油汚れが壁紙に染み込むのを防ぎ、黄ばみやベタつきを抑えられます。
手垢
手垢は、壁に直接触れることで付く汚れで、特に人の手がよく触れる場所に集中して現れます。
スイッチ周りやドアノブの近く、通路沿いの壁などは日常生活の中で何度も手が触れるため、手垢が目立ちやすくなる場所です。
手垢は皮脂や汗、手の汚れが混ざったものなので、長期間放置すると壁紙に黒ずみや黄ばみとして定着します。
手垢を防ぐためには、こまめな掃除が大切です。湿った布や中性洗剤を使ってやさしく拭くことで、汚れの蓄積を防ぐことができます。
また、汚れがひどくなる前に壁用クリーナーやスポンジを使用すると、黒ずみを効率的に落とせます。
クレヨンやペン
特に子どもがいる家庭では、壁にクレヨンやペンで落書きされることがよくあります。
汚れの種類は筆記具によって異なり、水性か油性かで落とし方も変わります。
水性ペンやクレヨンであれば、濡れた布や中性洗剤を溶かした水で拭き取ることが可能ですが、油性ペンやマジックの場合は通常の水拭きだけでは落としきれません。
クレヨンの油分が壁紙に染み込むと、時間が経つほど落としにくくなるため、早めの対処が大切です。
ビニールクロスのような表面がツルツルしたものは比較的拭き取りやすいですが、紙製や布製の壁紙は汚れが浸透しやすく、シミになりやすいため注意しましょう。
カビ
壁に発生するカビは、結露や湿気が多い場所で多く見られます。
特に窓際や水まわり、雨漏りしている部屋では、黒いポツポツとした汚れが壁に現れますが、実は汚れではなくカビそのものです。
放置すると壁紙だけでなく、壁内部まで侵食する可能性があるため早めの対策が重要です。
対策としては、まずは換気をして湿度を下げることが基本です。
窓を定期的に開けて、除湿器や換気扇を活用して空気の流れを確保することで、カビの発生リスクを減らせます。
また、カビが付着している場合は漂白剤や専用のカビ取り剤を使って丁寧に掃除して、しっかりと乾燥させることが大切です。
タバコ
室内でタバコを吸う場合、煙に含まれるヤニが壁に付着して黄ばみやベタつき、黒ずみとなります。
煙は空気中を漂いながら壁や天井に付着するため、長期間放置すると汚れが蓄積されて、見た目が悪くなるだけではなく独特の嫌な臭いも室内に残ってしまいます。
タバコのヤニは油分を含むため、水拭きだけでは落ちにくく、専用のクリーナーやアルカリ性洗剤を用いた丁寧な掃除が必要です。
なお、ヤニ汚れは一度つくと完全に除去することが難しいため、こまめな掃除や換気を習慣化することが壁紙を美しく保つポイントとなります。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!壁紙の汚れ落としに必要な洗剤やアイテム
壁紙の汚れ落としには、次のような洗剤やアイテムが有効です。
それぞれ有効な汚れの種類が異なるため、適切に使い分けましょう。
| 洗剤・掃除アイテム | 有効な汚れ |
|---|---|
| 中性洗剤 | 手垢・油汚れ・クレヨンやペンの汚れなど |
| アルカリ性洗剤(重曹・セスキ炭酸ソーダ) | こびりついた油汚れ・タバコのヤニ汚れなど |
| アルコールスプレー | カビ |
| 雑巾やモップ | ホコリ |
中性洗剤
中性洗剤は、壁紙の汚れを落とす際の基本的な洗剤として非常に便利です。
特に普段の掃除や軽い汚れの除去に向いており、黒ずみや手垢、調理中に付いた油汚れ、クレヨンやボールペンによる軽い落書きなど幅広い汚れに対応できます。
使い方もシンプルで、水で薄めてスポンジや柔らかい布に含ませて、やさしく壁紙を拭くだけで完了です。
ただし、壁紙の種類によっては水分や摩擦に弱い場合があるため、最初に目立たない箇所で試すことが大切です。
また、拭き掃除のあとは水拭きや乾いた布で洗剤をきれいに拭き取ることで、洗剤の成分が壁紙に残って黄ばみや変色を引き起こすリスクを防げます。
アルカリ性洗剤(重曹・セスキ炭酸ソーダ)
重曹やセスキ炭酸ソーダなどのアルカリ性洗剤は、中性洗剤では落ちにくい頑固な汚れに効果を発揮します。
特に油や調味料による頑固なべたつきやタバコのヤニ汚れ、クレヨンやボールペンのしつこい落書き、大型家具の裏にたまった黒ずみなどを、強力なアルカリ性成分で分解できます。
使い方は簡単で、重曹やセスキ炭酸ソーダを水に溶かしてペースト状にしたり、水溶液にして布やスポンジに含ませて、汚れた部分をやさしく拭き取るだけです。
また、重曹やセスキ炭酸ソーダは粉末のままでは壁紙に直接使えないため、水に溶かしてから使用することがポイントです。
なかでも油汚れは時間が経つと固まってしまうので、見つけ次第早めにアルカリ性洗剤で拭き取ることで、掃除の手間を大幅に減らせます。
アルコールスプレー
消毒用アルコールスプレーは、壁紙のカビ汚れに特化した掃除アイテムです。
特に結露や湿気が原因で発生した黒ずみのようなカビには、アルコールの殺菌作用が有効で、壁紙の表面からカビを取り除きつつ再発も防ぎやすくなります。
使用する際は、まずは目立たない部分で試し拭きして、壁紙に変色やダメージが出ないかを確認することが大切です。
また、カビを拭き取ったあとは、残ったアルコールを乾いた布でしっかりと拭き取り、壁紙に液体が残らないようにしましょう。
定期的に壁の状態をチェックして、カビの初期段階で処置することで広がりを防ぎ、壁紙を長持ちさせることが可能です。
雑巾やモップ
壁紙の汚れを落とす際は、掃除道具として雑巾やモップを使用しましょう。
特に普段のホコリや軽い汚れの除去には、乾いた柔らかい雑巾やマイクロファイバーのモップなどが効果的です。
壁紙は摩擦や水分に弱い場合があるため、強くこすらず雑巾やモップで軽く撫でるように掃除することがポイントです。
また、掃除後は乾いた布で水分をしっかりと拭き取り、カビや水跡が残らないようにすることが大切です。
モップを使用すると、高い場所や広い面積の掃除もスムーズに行えます。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!【要チェック】壁の素材ごとの掃除方法の違い
壁紙にはさまざまな素材が使われており、素材ごとに適切な掃除方法が異なります。
ここでは、主に次のような壁紙の掃除方法の違いを解説します。
壁紙の素材別掃除方法
・ビニールクロス
・和紙・布・珪藻土
ビニールクロス
ビニールクロスは、日本の住宅で最も多く使われている壁紙で、水や汚れに強く掃除しやすい点が特徴です。
表面がビニールでコーティングされているため、軽い汚れや手垢、油汚れやホコリなどは固く絞った雑巾やスポンジで拭き取るだけで落とせます。
頑固な汚れがある場合は、中性洗剤を水で薄めた溶液を布に付けて拭き取ると効果的です。
高い場所や家具の裏側などの届きにくい部分には、モップやはたきを使うのがおすすめです。
また、掃除前には目立たない箇所で洗剤を試すことで色落ちを防ぐことができます。
和紙・布・珪藻土
和紙や布、珪藻土などの自然素材の壁は、水や洗剤に弱くビニールクロスのように簡単に拭き掃除ができません。
特に和紙や織物壁紙は、濡れた布で拭くとシミや変色の原因になるため、基本的には乾いた布や柔らかいはたきでホコリを払うようにしましょう。
そのため、柔らかいほうきやはたきでやさしくホコリを落とすことが大切です。
紙壁紙も水分に弱く、撥水加工されていない場合は特に注意が必要で、乾いた布での掃除が基本となります。
これらの素材は、水拭きや洗剤の使用によって壁紙の劣化やシミ、変色のリスクがあるため、必ず取扱説明書やメーカーの推奨方法を確認しながら掃除を行ってみてください。
【汚れ別】壁紙の掃除方法
ここからは、壁紙に付着しやすい次のよくある汚れ別に、詳しい掃除方法を紹介します。
壁紙の汚れ別掃除方法
・手垢・油汚れ・クレヨンやペンの汚れ
・こびりついた油汚れ・タバコのヤニ汚れ
・カビ汚れ
・ホコリ
手垢・油汚れ・クレヨンやペンの汚れ
手垢や調理中の油汚れ、子どもの落書きによるクレヨンやペンの汚れは、中性洗剤を使うと比較的簡単に落とせます。
掃除の手順は次のとおりです。
- 水に濡らして固く絞った雑巾に、中性洗剤を数滴ほど垂らす
- 中性洗剤をつけた雑巾で、壁の汚れをやさしく拭き取る
- 雑巾を水洗いして、洗剤がついていない状態で水拭きする
- 別の乾いた雑巾で水分や洗剤が残らないように乾拭きする
まず、雑巾に少量の中性洗剤をつけることで、汚れを浮かせやすくなります。
油汚れや手垢は固くなっている場合があるため、力を入れすぎずなでるように拭くことが大切です。
最後に乾拭きすることで、洗剤や水分が残らず壁の変色やシミを防ぐことができます。
こびりついた油汚れ・タバコのヤニ汚れ
キッチン周りの壁や喫煙する部屋の壁は、油やタバコのヤニが付着しやすく、放置すると頑固な汚れになります。
このような汚れは中性洗剤だけでは落ちにくいため、重曹やセスキ炭酸ソーダなどのアルカリ性洗剤を活用すると効果的です。
掃除の手順は次のとおりです。
-
重曹またはセスキ炭酸ソーダを水に溶かしてアルカリ性溶液を作る
-
作った溶液をスプレーボトルに入れて、汚れ部分に吹きかける
-
下から上に向かって、壁の汚れを拭き取る
-
溶液が残らないよう、濡れた雑巾で水拭きする
-
乾いた雑巾で乾拭きして仕上げる
アルカリ性洗剤は油分やタバコのヤニを分解し、汚れを浮かせる効果があります。
吹きかけた溶液をそのままにすると垂れ跡が残るため、必ず下から上に拭き上げるようにしましょう。
定期的に掃除することで、黄ばみやベタつきの頑固な蓄積を防ぎ、壁の印象を清潔に保てます。
特にキッチンや喫煙室は汚れが目立ちやすいため、週に1回程度の頻度で軽い拭き掃除を行うと、頑固な汚れが付く前に対処できます。
カビ汚れ
壁紙に発生するカビは、主に湿気や結露が原因で発生します。窓際や水まわり、雨漏りのある部屋などでは特に注意が必要です。
カビは汚れとは異なり、放置すると壁内部まで浸透して腐食や悪臭の原因となるため、早期に対処しましょう。
具体的な掃除の手順は、次のとおりです。
-
消毒用アルコールを雑巾や布に染み込ませて、目立たない場所で壁紙への影響を確認する
-
カビ汚れをアルコールで丁寧に拭き取る
-
拭き取り後、水分やアルコールが残らないよう乾いた雑巾で乾拭きする
-
必要に応じて換気を行い、湿気を減らす
消毒用アルコールは殺菌効果が期待でき、壁紙に直接ダメージを与えにくい点がメリットです。
また、掃除後に換気や除湿を行うことで再発を防ぎ、カビが発生しにくい環境を作れます。
カビは放置すると拡大しやすく、壁紙の耐久性にも影響するため、発見したらすぐに掃除する習慣を身につけることが清潔な室内環境の維持につながります。
ホコリ
壁に付着するホコリは、空気中を漂う綿ぼこりや砂ぼこり、花粉などが積もることで発生します。
特に家具の裏側や高い場所、あまり掃除が行き届かない隅の壁には黒ずみとして目立つことが多く、放置すると壁紙の見た目が悪くなるだけではなく、アレルギーや喘息の原因になることもあります。
そのため、以下の手順で掃除しましょう。
-
壁の上部にモップやクロスを押し当てる
-
上から順に、左右に大きなS字を描くようにしてホコリを落とす
-
掃除後に、床や家具に落ちたホコリを掃除機や掃き掃除で取り除く
-
定期的に1ヶ月に1回程度の頻度で掃除を行う
ホコリ掃除には、ハンディタイプや伸縮タイプのモップなど、壁の高い部分にも届く道具を使うと便利です。
柔らかいファイバーがホコリを舞い上げずにキャッチするため、効率よく掃除できます。
ホコリは小さな汚れですが蓄積すると見た目が悪くなるため、日常的に軽く掃き掃除をする習慣を身につけるだけでも、室内の清潔さを保てるようになるでしょう。
また、換気を併用することで空気中のホコリの滞留を減らし、よりきれいな壁を維持できます。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!掃除後の壁の汚れを防ぐ方法は?
掃除をして壁紙がきれいになっても、そのままにしておくと再び汚れが付着してしまいます。
汚れの付着を防いで掃除頻度を減らしたい場合は、次の3つの方法を試してみてください。
壁紙の汚れ防止方法
・ホコリがついていたらすぐに落とす
・こびりついた油汚れ・タバコのヤニ汚れ
・こまめに換気する
・壁から家具や家電を離す
ホコリがついていたらすぐに落とす
壁に付着したホコリは、放置すると黒ずみや汚れの原因となり、掃除をしても落としにくくなります。
特に凹凸のある壁紙や家具の裏側などは、ホコリが溜まりやすくいためこまめな掃除が必要です。
まずは、ハンディモップや柔らかい布などを使い、壁の上部から下部へ順番にホコリを払います。
ハンディモップがない場合は、古いストッキングを棒に巻き付けて代用すると静電気でホコリを吸着できて便利です。
また、掃除の際は一度に広範囲をこすらず、軽く払いながら丁寧に行うことで壁紙を傷めにくくなります。
特に季節の変わり目や窓を開ける機会が多い時期は、ホコリが舞いやすくなるため、週に1回程度の簡単な掃除を行ってみてください。
こまめに換気する
壁紙の汚れ防止には、換気が非常に重要です。特にタバコの煙や調理中の油煙・湯気などは、壁紙に付着して黄ばみやベタつきの原因になります。
キッチンでは調理中に換気扇を回して、換気扇自体も定期的に掃除してフィルターやファンに溜まった汚れを落とすことで、排気効率が向上し、壁紙への付着を防ぎやすくなります。
ただし設置場所には注意が必要で、壁に近すぎたり白い壁の近くに置いたりすると、空気清浄機周辺に汚れた空気が集まって逆に壁紙が汚れることがあります。
理想としては壁から少し離して設置し、部屋全体の空気が循環するように調整しましょう。
壁から家具や家電を離す
家具や家電を壁にピッタリとくっつけて設置すると、静電気が発生してホコリが壁に吸着しやすくなります。
また、壁と家具の間に湿気がこもることで、カビや結露の原因となる場合もあるため注意が必要です。
そのため、家具や家電は壁から少し離して設置することが重要といえます。
隙間を設けることで、壁と家具の間に空気の流れが生まれて、湿気や汚れの滞留を防げます。
さらに、掃除機やモップで簡単に隙間を掃除できるため、ホコリや汚れが溜まるのを防ぐ効果も期待できます。
特に結露が発生しやすい冬場や湿気の多い季節は、家具を壁から離して設置することが壁紙の黄ばみやカビの防止につながるでしょう。
落ちない壁紙の汚れはハウスクリーニングがおすすめ
壁紙の汚れは、日常の掃除である程度は落とせますが、長年放置された黄ばみやタバコのヤニ、頑固な油汚れやカビなどは、自力では完全に取り除くのが難しい場合があります。
特に、汚れが染み付いてしまった壁や、洗剤や水拭きでも効果が薄い場合は、自分で無理に落とそうとすると壁紙を傷めたり変色させたりしてしまうリスクもあるため危険です。
このように、自分で掃除しても汚れを落とせない場合は、プロによるハウスクリーニングを活用するのが効果的です。
また、頑固なカビやヤニ汚れにも対応できるため、壁紙の美しさを短時間で回復させることが可能です。
さらにハウスクリーニングでは、壁だけではなく天井やエアコン周辺など、汚れが広がりやすい場所も同時に掃除してもらえる点もメリットです。
壁紙以外の幅広い範囲も同時に掃除してもらえるため、室内の汚れをまとめてきれいにしたい場合におすすめといえます。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!壁紙の汚れ落としに関するよくある質問
壁紙は汚れていなくても、定期的に掃除しましょう。一見汚れていなくても空気中のホコリや細かな汚れが付着していることが多く、そのまま放置するとカビの発生や嫌な臭いの原因になる場合があります。また、壁は部屋の面積の大部分を占めるため、汚れが蓄積されると部屋全体が暗くくすんで見えることもあります。さらに、賃貸物件では退去時の原状回復に関わるので、壁紙を定期的に掃除して清潔さを保っておきましょう。ハンディモップやクロスを用いて月に1回程度の掃除を行うと、壁紙の美しさと衛生状態を維持できます。
白い壁紙の黒ずみを落とすには、軽い汚れであれば中性洗剤を使った掃除が効果的です。まず、水で濡らして固く絞った雑巾に中性洗剤を少量含ませ、黒ずみ部分をやさしく拭きます。そして洗剤が残らないように水で濡らして軽く絞った雑巾で再度拭き取り、最後に乾いた雑巾で水分を完全に拭き取りましょう。頑固な汚れには、少量の重曹水やセスキ炭酸ソーダ水を使って、下から上へやさしく拭く方法もおすすめです。
頑固な汚れには、、水から作られた「水の激落ちくん」が便利です。皮脂汚れやキッチンの油汚れなど、普段の掃除では落ちにくい汚れもスプレーして拭くだけで簡単に除去できます。界面活性剤不使用で使用後の二度拭きが不要で、除菌・消臭効果もあるため、衛生面や臭い対策にも役立ちます。
定期的な掃除で壁紙の汚れを防ごう
壁紙の汚れを防ぐためには、定期的なお手入れが欠かせません。目に見える汚れだけではなく、ホコリや皮脂、タバコのヤニなどは日常生活の中で少しずつ蓄積されます。
特に白や淡色の壁は汚れが目立ちやすく、部屋全体の印象にも影響するため、月に1回を目安に雑巾やハンディモップなどで軽く拭き掃除を行うことがおすすめです。
また、換気や家具の配置に気をつけることで、汚れの付着を防ぐことも可能です。
自宅での掃除で落としきれない頑固な汚れやヤニ、カビなどには、プロのハウスクリーニングの利用も検討してみてください。
| 地域 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。
※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。
※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する










