フローリングのカビ取りのやり方は?必要なアイテムや予防策などを紹介
更新日:
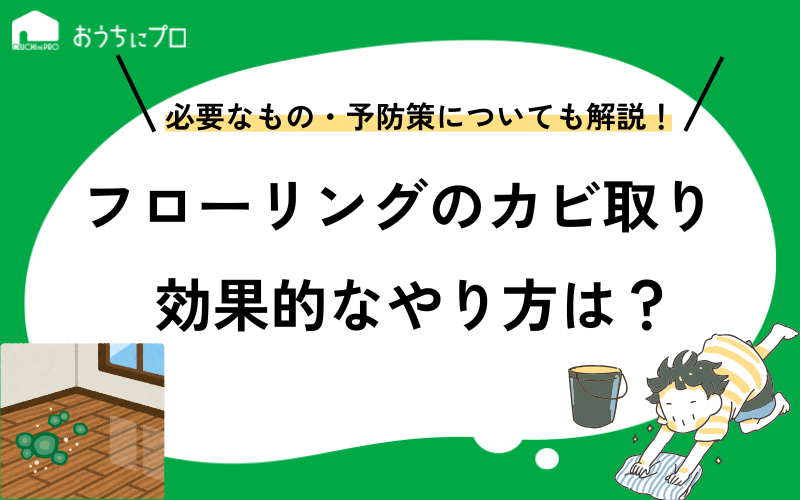
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する「フローリングに黒ずんだカビ汚れがある」「きれいに取り除いて、もうカビが生えないようにしたい」とお悩みの方も多いでしょう。
フローリングにこぼした水分を放置したり、長期間カーペットを敷きっぱなしにしていたりすると、カビが生えてしまうことがあります。
無水エタノールなどを使って自分で取り除くことができますが、深く根を張ったカビは取り除くのが困難になるため、早めに対処を行いましょう。
本記事では、フローリングにカビが生える主な原因や、具体的なカビ取り方法を詳しく解説します。
頑固なカビの対処法や、カビの再発を防ぐ方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- この記事でわかること
-
- ・フローリングは、結露や飲み物をこぼした際の水分、観葉植物やカーペットの湿気などによってカビが生えやすい
- ・エタノール水をかけてブラシや雑巾でやさしくこすると、ほとんどのカビはきれいに落とすことが可能
- ・深くまで根を張ったカビは落としづらいため、プロによるハウスクリーニングを依頼するのがおすすめ
- ・掃除機でカビを吸ったり、塩素系漂白剤や酢・重曹などを使ったりする掃除は、床面を傷めたり健康被害が生じたりするため避けた方がよい
- ・除湿や換気を心がけて、フローリングを常に清潔に保つことがカビを防ぐための基本
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!目次
- 【記事作成】おうちにプロ 編集部
- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!
フローリングにカビが生える原因とは?
自宅のフローリングには、主に次のような原因によってカビが生えることがあります。
フローリングにカビが生える原因
・結露で発生した水分
・飲み物をこぼした際に放置した水分
・長期間敷いているカーペット
・観葉植物
結露で発生した水分
窓や外壁の表面が冷えると、部屋の暖かい空気中に含まれる水蒸気が凝結して水滴になります。
このときに発生した結露水が窓枠から滴り落ちたり、窓際の床に染み込んだりすると、フローリング表面に長時間水分が残るためカビが繁殖しやすくなります。
結露は見た目は小さな水滴でも、繰り返し濡れることでフローリングの継ぎ目に水分が入り込み、細かなゴミやホコリなどと合わさってカビの栄養源になってしまいます。
予防するためには、まずは結露を見つけたらすぐに拭き取り、換気をして湿度を下げることが大切です。
窓周りの断熱を強化すると結露そのものを減らせるほか、加湿のしすぎを控えたり室内干しの際は換気を徹底したりするなど、ほんの少しの工夫も効果的です。
飲み物をこぼした際に放置した水分
フローリングに飲み物をこぼしたとき、すぐに拭き取らずにそのまま放置してしまうと、木材の隙間から水分が染み込んでカビが繁殖する原因になります。
コーヒーやジュースのような糖分などを含む飲料は、カビにとって大きな栄養源となるため繁殖リスクがさらに高まります。
特に湿度が60%を超える環境では、わずかな水分量でもカビの繁殖が進みやすくなります。
対応としては、飲み物をこぼしたらすぐに乾いた布やペーパーでしっかりと吸い取り、水拭きと乾拭きを徹底することが大切です。
さらに室内の風通しを良くして、扇風機や除湿機で乾燥を早めれば内部まで乾きやすくなります。
長期間敷いているカーペット
カーペットやラグをフローリングに長期間敷いたままにしていると、通気性が悪くなって湿気がこもりやすくなります。
特に夏場や梅雨の時期は床面に熱と湿気が溜まり、カビが発生しやすい環境が整ってしまう点に気をつけなければなりません。
さらに、カーペット自体に汗や皮脂、食べカスやホコリなどが付着すると、カビの栄養源となって繁殖スピードを速めてしまいます。
また、重たい家具をカーペットの上に置いていると、空気の流れがさらに遮られてしまい、湿気が逃げにくくなるため注意が必要です。
対策としては、定期的にカーペットを取り外して床面を乾燥させて、掃除機で細かなゴミも掃除することが効果的です。
さらに、丸洗いできる素材のカーペットを選んだり、除湿シートを併用したりするのもおすすめです。
観葉植物
観葉植物は室内を彩るほか、リラックス効果も期待できるため人気がありますが、置き方によってはフローリングのカビの発生源になってしまいます。
具体的には、鉢植えに水を与えた際に受け皿へ水が溜まり、そのまま水分が蒸発せずに残っていると、床に湿気が伝わってカビの温床となってしまうのです。
また、植物そのものから発せられる水分によって周囲の湿度が高くなると、窓際や日当たりの悪い場所では乾燥が追いつかずに湿気がこもることもあります。
さらに、土には有機物が多く含まれており、床にこぼれた際にカビの栄養源になりやすい点にも注意が必要です。
対策としては、必ず受け皿を使用して定期的に乾いた布で皿や床面を拭いたり、鉢を直接床に置かずにスタンドやマットを使用したりすることが有効です。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!フローリングのカビ取りに必要なアイテム
カビを安全に落とすためには、効果的なアイテムを揃える必要があります。
フローリングのカビ取りに必要な主なアイテムは、次の5つです。
フローリングのカビ取りに必要なアイテム
・無水エタノール
・スプレーボトル
・ゴム手袋
・ブラシ
・雑巾やキッチンペーパー
無水エタノールは消毒効果が高く、フローリングの表面に広がったカビ菌をしっかりと除去する効果が期待できます。
原液のまま使うと揮発が早すぎるため、水で薄めてからスプレーボトルに入れると使いやすくなります。
さらに、フローリングの溝や細かい部分に入り込んだカビは、雑巾だけでは取り切れないことがあります。
細かな部分の掃除には歯ブラシや小さめのブラシを使うと、木目に沿って効率的にかき出すことが可能です。
これらのアイテムを使用する際の注意点は再利用をしないことで、再利用するとカビの菌を別の場所に広げる原因となるため、必ず使い捨てるようにしましょう。
【3ステップ】フローリングのカビ取りをする方法
フローリングのカビは、次の3ステップを実践すると自分で取り除くことが可能です。
フローリングのカビ取りの3ステップ
①換気してマスクを着用する
②カビにエタノール水をスプレーして拭き取る
③掃除した場所を乾拭きして乾燥させる
①換気してマスクを着用する
フローリングのカビ取りを始める際には、まずは部屋をしっかりと換気することが欠かせません。
カビ掃除を行うと、目に見えない胞子が空気中に舞い上がります。
誤って胞子を吸い込んでしまうと、アレルギー反応や体調不良を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
特に湿気がこもりやすい部屋では、掃除の前から換気を徹底しておくことで快適に作業に取り組めます。
また、換気と同時にマスクの着用も忘れてはいけません。
カビは胞子の大きさが非常に小さいため、通常のホコリよりも吸い込みやすい点が特徴です。
作業中に吸い込んでしまうと喉の痛みや咳が出ることもありますが、マスクを着けることで舞い上がった胞子を直接吸い込むリスクを軽減できます。
②カビにエタノール水をスプレーして拭き取る
次にカビを掃除していきますが、エタノール水を実際に使う前に、まずは多くの家庭のキッチンにある中性洗剤を試してみるのがおすすめです。
カビが目に見えている部分に中性洗剤を吹きかけて、5分ほど置いておくと汚れが浮き上がりやすくなります。
雑巾を固く絞ってから拭き取れば、軽度のカビであればほとんど除去できることもあるため、ぜひ試してみてください。
しかし、中性洗剤だけでは落としきれないカビも少なくないため、頑固なカビにはエタノール水を使用しましょう。
一度に大量にかけるとフローリングにシミや変色が生じるおそれがあるため、少量をまんべんなく行き渡らせるのがポイントです。
フローリングの溝に入り込んだカビは、ブラシを使ってかき出すと効果的です。
③掃除した場所を乾拭きして乾燥させる
エタノール水でカビを拭き取ったあとは、フローリングを完全に乾燥させることが大切です。
濡れたまま放置すると、残った水分によって再びカビが繁殖してしまう可能性があります。
まずは、使い捨ての乾いた雑巾やキッチンペーパーを使って、拭き取り残しがないか確認しながら全体を丁寧に乾拭きしてみてください。
乾拭きする際は、フローリングを強くこすりすぎないようにしましょう。
強くこするとフローリングの表面に傷がついたり、ワックスや塗装が剥がれたりすることがあるため、あくまでもやさしくまんべんなく拭き上げることがポイントです。
乾拭きが完了したら、できるだけ室内の湿度を下げるために、窓を開けたり換気扇を回したりして空気の流れを作りましょう。
さらに、可能であれば扇風機やサーキュレーターを使って空気を循環させると、乾燥が早くなりカビの再発リスクを減らせます。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!誤ったカビ取り方法に注意が必要
フローリングに繁殖したカビを取り除くには、エタノールを使った掃除が正しい方法です。
しかし、次のような誤った方法でカビ取りを行うと、床面を傷めたり健康被害が生じたりする可能性があるため気をつけましょう。
フローリングのカビ取りの誤った方法
・掃除機でカビを吸う
・塩素系漂白剤で掃除する
・酢や重曹を使って掃除する
掃除機でカビを吸う
フローリングに生えたカビを見つけた際に、手軽だからといって掃除機で吸い取るのは非常に危険です。
カビの胞子はとても細かく、掃除機のフィルターを通り抜けてしまうことがあります。
その結果、カビを吸引したつもりでも掃除機の排気口からカビの胞子が部屋全体に拡散されて、別の場所に新たなカビを繁殖させる原因となってしまいます。
また、掃除機のブラシやヘッド部分に付着した胞子が残ると、次回掃除をした際に別の部屋やフローリングにカビを広げてしまう可能性もあります。
掃除機を使うと一見効率的ですが、カビの除去としては逆効果になる場合がほとんどです。
そのため、掃除機ではなく無水エタノールをスプレーして拭き取る方法が安全で効果的です。
塩素系漂白剤で掃除する
フローリングのカビを落とそうとして、カビキラーやキッチンハイターのような塩素系漂白剤を使うのは避けましょう。
塩素系漂白剤は強力なアルカリ性の性質を持っているため、フローリングの木材や塗装を傷めてしまう可能性があります。
特にワックス加工が施されているフローリングでは、表面のワックスが剥がれてしまい、変色や白化が起こることも少なくありません。
換気によって健康被害を防げますが、それでもフローリングの材質を傷めるリスクは避けられません。
なお、賃貸住宅の場合は床の変色や損傷が原状回復の対象になり、退去時に補償を求められる場合もあります。
酢や重曹を使って掃除する
フローリングのカビ取りに、酢や重曹を使うのもおすすめできません。
酢は酸性の液体で一部のカビには効果が期待できますが、フローリングに使うと表面がべたつきやすく、乾いたあとにシミや変色が残ることがあります。
重曹は研磨作用を持つため、フローリングのワックスや塗装を削ってしまうことがあります。
見た目の傷やツヤの喪失につながり、フローリングの寿命を縮めてしまうおそれがあるため注意しましょう。
特に古い床やワックス加工されているフローリングでは、目立つダメージが残る可能性が高いです。
フローリングの頑固なカビにはハウスクリーニングが有効
フローリングのカビが広範囲にわたって繁殖してしまった場合や、自分で掃除しても落とせないような頑固なカビ汚れには、プロの業者に依頼するハウスクリーニングが有効です。
プロの専門業者であれば、専用の洗浄剤やブラシ、機材などを駆使して、一般的な掃除では取り切れないカビや汚れも効率的に除去できます。
特に、フローリングは水分や湿気によってカビが根を張りやすいため、表面だけでなく溝や隙間まで丁寧に掃除できるプロの技術が役立ちます。
部屋ごとの汚れにあわせて薬剤や道具を使い分けて、カビや油汚れ、ホコリや皮脂などを徹底的に除去してくれます。
また、作業範囲は部分的な掃除から家全体の掃除まで柔軟に対応できるため、必要な場所だけを重点的にきれいにすることも可能です。
定期的にハウスクリーニングを依頼すれば、部屋の清潔度を長期間維持することができ、日常の掃除の手間を大幅に減らせます。
ハウスクリーニングの料金相場
ハウスクリーニングにかかる料金は、基本的には自宅の広さや間取りによって大きく変動します。
一般的に部屋が広いほど作業面積も増えるため、料金は高めに設定される傾向がある点が特徴です。
また、一戸建ての場合は階段や複雑な間取りの影響で、マンションやアパートに比べて料金が高くなるケースが多いでしょう。
次の表に、一戸建てとマンション・アパートにおける間取り別の料金相場をまとめました。
| 間取り | 一戸建て | マンション・アパート |
|---|---|---|
| 1R・1K | – | 18,000円~23,000円 |
| 1DK・2K | – | 20,000円~30,000円 |
| 1LDK・2DK | – | 28,000円~40,000円 |
| 2LDK・3DK | 60,000円~100,000円 | 40,000円~50,000円 |
| 3LDK・4DK | 70,000円~110,000円 | 50,000円~65,000円 |
| 4LDK・5DK〜 | 80,000円~140,000円 | 65,000円~ |
上に挙げたものはあくまで基本料金の目安であり、家具の養生や特別な清掃オプションを依頼する場合は追加料金が発生する可能性があります。
入念に準備をしてから依頼することで、予算にあったサービスを選ぶことができ、納得のいくクリーニングが実現できるでしょう。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!ハウスクリーニング業者の選び方
ハウスクリーニング業者を選ぶ際は、次の選び方を参考にしてみてください。
ハウスクリーニング業者の選び方
・料金から選ぶ
・過去の実績や技術で選ぶ
・損害賠償保険の加入有無で選ぶ
・口コミや評判のよさで選ぶ
まず、依頼前に必ず見積もりを取り、料金の内訳と作業内容が明確に記載されているかを確認しましょう。
あいまいな表記の業者は追加料金が発生するなどのトラブルの原因になりやすいほか、相場よりも安すぎる場合も特に注意が必要です。
次に、業者のホームページやパンフレットで過去の実績やビフォーアフター写真を確認して、どれだけの技術力を備えているのかをチェックしましょう。
あわせて損害賠償保険の加入有無も重要なポイントです。たとえプロであっても作業中に家具や壁、床を傷つけてしまう可能性はゼロではありません。
最後に、口コミや評判のチェックも欠かせません。
Googleマップや口コミサイトなどから依頼したい業者の評価を確認して、良い点と悪い点を客観的に判断しましょう。
たとえ悪い評価があっても、内容を確認して許容できる範囲であれば問題ありません。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!フローリングのカビを再発させないための予防策
フローリングのカビをきれいに取り除いたあとは、再発を防ぐために次のような予防策を行いましょう。
フローリングのカビの予防策
・フローリングを常に清潔にする
・除湿や換気を心がける
・カーペットは定期的に干す
・フロアコーティングを施す
フローリングを常に清潔にする
フローリングのカビ予防の基本は、日常的に清潔な状態を保つことです。
ホコリや髪の毛、食べカスなどのゴミはカビの栄養源になりやすく、放置してしまうとわずかな水分でも繁殖のきっかけになります。
特にカーペットやマットの下は湿気や汚れが溜まりやすく、定期的にめくって掃除機をかけるだけでも予防効果が高まります。
週に数回でもホコリを取り除く習慣を身につけると、湿気の多い季節でもカビの発生リスクを大幅に下げられます。
布団やマットレスをフローリングの上に直接敷く場合も、下にすのこや新聞紙を敷いて通気性を確保することで、湿気を溜め込まずに清潔な状態を保てるようになります。
除湿や換気を心がける
フローリングのカビを防ぐためには、室内の湿度をコントロールすることが重要です。
カビは湿度60%以上、気温20〜25度程度で繁殖しやすいとされているため、特に梅雨や冬の結露が発生しやすい時期は注意しましょう。
除湿器を活用して定期的に湿度を下げるほか、風通しの悪いクローゼットや洗面所などは扇風機を使用して空気を循環させるのがおすすめです。
2ヶ所以上の窓を開けて風の通り道を作るとさらに換気効率が高まり、フローリングに湿気や水分が留まりにくくなります。
さらに、結露が発生した場合は雑巾やタオルでこまめに拭き取る習慣を身につけると、カビの発生リスクを大幅に抑えることが可能です。
カーペットは定期的に干す
フローリングに敷いたカーペットやマットは、湿気が溜まるとカビの温床になりやすいため、定期的に風に当てて乾燥させることが大切です。
特に湿気がこもりやすい季節や、長期間敷きっぱなしにしている場合は、カーペットの下に湿気が溜まってフローリングまで湿度が上がってしまいます。
もし毎回完全に干すのが難しい場合は、床掃除のタイミングでカーペットの半分をめくり、1時間ほど空気に触れさせるだけでもカビを防ぐ効果が期待できます。
また、カーペットの素材によっては吸湿性が高く、湿気を長く保持してしまうものもあるため特に注意しましょう。
フロアコーティングを施す
フローリングのフロアコーティングは、カビの再発防止に対して非常に効果的です。
フロアコーティングは、耐久性の高い保護膜をフローリング表面に作ることで、傷や汚れが付きにくくなるだけではなく、湿気や水分が直接木材に浸透するのを防ぎます。
結果として、カビが繁殖しにくい環境を作ることが可能です。
また、コーティングによって雑巾で軽く拭くだけで汚れを落とせるため、日常のメンテナンスの負担も大幅に軽減できます。
施工は専門の業者に依頼するのが一般的で、床材に合わせた最適なコーティング剤を選んでくれるため、仕上がりも安心といえるでしょう。
フローリングのカビ取りに関するよくある質問
範囲が狭い場合は、フローリング用のクレヨンを活用するのが有効です。フローリングの色にあわせたクレヨンで目立つカビ部分を塗りつぶすことで、見た目を整えられます。色合いが微妙に異なる場合は、二色以上を組み合わせるとより自然に仕上がるでしょう。広範囲にカビが広がってしまった場合は、木目調のカーペットやラグを重ねて敷く方法もあります。費用が少しかかりますが、手軽に見た目をカバーできるため、急な来客時などに役立ちます。ただし、これらの方法はあくまで一時的な応急処置なため、しっかりと掃除してカビを根本から取り除くことが大切です。
窓を開けて風通しをよくしたり、扇風機で空気を循環させたりすることで湿気を減らすことは可能です。しかし、湿度が高い日本の住宅環境では、自然乾燥だけで湿気を十分に取り除くことはできず、カビを完全に防ぐのは難しいといえます。特に冬場の結露や梅雨のような湿度が高い時期は、フローリング表面や床下に水分が残りカビが生えやすくなります。そのため、自然乾燥に加えて除湿機やエアコンの除湿機能を活用するほか、定期的に窓辺の水分を拭き取るなどの対策を組み合わせることが大切です。
賃貸物件でフローリングにカビが生えてしまった場合は、自己判断で無理に掃除せずに大家や管理会社に相談するのが基本です。自力でこすったり、塩素系漂白剤などの強力な薬剤を使用してフローリングを傷めてしまうと、借主の過失とみなされて修繕費用を請求される可能性があります。そのため、専門業者に依頼することも含めて、大家や管理会社の指示に従いましょう。経年劣化によって生じたカビであれば、退去時に費用を請求されることは少ないです。ただし、換気不足などの不注意の場合は費用を請求されることがあるため注意しましょう。
フローリングのカビは見つけたらすぐに対処しよう
フローリングにカビを見つけたら、放置せずにすぐに対処することが大切です。
軽度であれば無水エタノールや中性洗剤を使った掃除で落とせますが、範囲が広い場合や頑固なカビは、自分で掃除しても十分に取り切れないこともあります。
頑固なカビの掃除には、プロのハウスクリーニングを依頼するのがおすすめです。
専用の薬剤や器具でフローリングを丁寧に掃除してもらえるため、再発防止にもつながります。
| 地域 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。
※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。
※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する










