窓サッシの簡単な掃除方法は?必要な道具やおすすめ頻度を紹介
更新日:
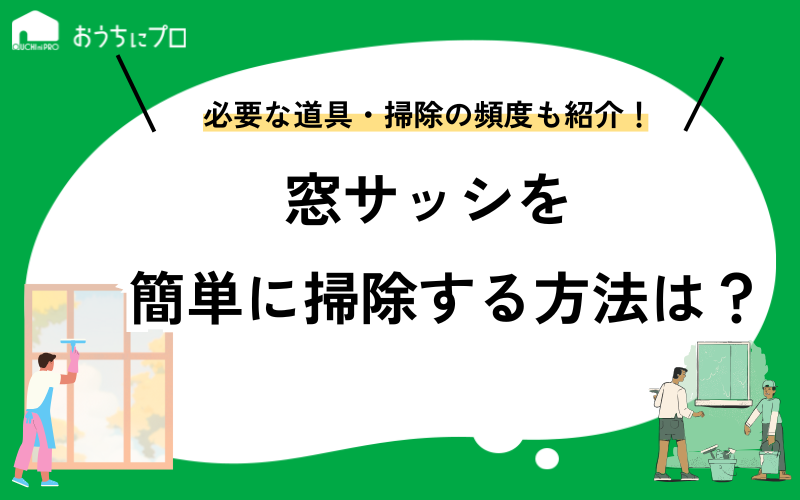
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する「窓サッシに汚れがびっしりと付いている」「頑固な汚れが落ちない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
窓サッシの汚れを放置すると、窓がスムーズに開閉できなくなったり、雨漏りが発生したりするおそれがあります。
自分で簡単に掃除できるため、こまめに掃除して汚れの蓄積を防ぎましょう。
本記事では、窓サッシの簡単な掃除方法と必要なアイテムを詳しく解説します。
窓サッシと同時に掃除できる窓ガラスや網戸の掃除方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- この記事でわかること
-
- ・窓サッシが汚れるのは、土埃や泥、花粉や油汚れのほかカビなどが原因
- ・基本的に自分で掃除できるが、頑固なカビが生えていない限りは洗剤の使用は不要
- ・簡単に落とせないカビが生えた場合は、重曹とクエン酸の粉末を混ぜて掃除するのが効果的
- ・簡単な掃除は月に1回程度、本格的な掃除は年に2回程度(5月、11月頃)を目安に行うのが最適
- ・頑固な汚れが残る場合は、プロによるクリーニングを依頼するのがおすすめ
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!目次
- 【記事作成】おうちにプロ 編集部
- ハウスクリーニングのプロが監修したお掃除や家事の時短アイディアや役立つアイテムをご紹介。毎日の暮らしをちょっと楽しく・ちょっと豊かにする情報を発信中!
窓サッシに付着しやすい汚れは?
窓サッシには、主に次のような汚れが付着することが多いです。
窓サッシに付着しやすい汚れ
・土埃や泥、花粉
・皮脂汚れや油汚れ
・カビ
・水アカ
土埃や泥、花粉
窓サッシに付着する汚れの中でも、特に外から持ち込まれる土埃や泥、花粉などは目立ちやすく、放置すると掃除が大変になります。
風に乗って飛んでくる砂や土、雨や風によって運ばれた泥は、サッシの溝や角に入り込みやすく、乾燥するとこびりついて取りにくくなる点に注意が必要です。
さらに、幹線道路の近くや建設現場の近くでは、排気ガスの粉じんや細かい砂などが混ざるため、黒ずんだ汚れとして目に見えることもあります。
花粉の粒子は細かいため水拭きだけでは完全に除去できず、ほかのホコリや泥と混ざることで頑固な汚れになりやすい特徴があります。
土埃や花粉は、定期的に掃除することでこびりつきを防ぎ、清潔な状態を保ちやすくなります。
特に溝や角に溜まった汚れは、放置すると水拭きの際に広がって掃除が面倒になるため、軽くブラシや掃除機でホコリを払うなどの日常的なケアが必要です。
皮脂汚れや油汚れ
窓サッシは、外からの汚れだけではなく、手で触れることによって付着する皮脂や油汚れも目立ちやすい場所です。
サッシの溝や角は手が届きやすく、掃除が行き届かないと手垢が蓄積して黒ずんで見えることがあります。
また、キッチン近くの窓サッシでは、調理中の油を含んだ空気や蒸気が付着することがあり、乾燥すると薄い油膜となってサッシに残ります。
さらに、油分を含んだ汚れはカビの栄養源になりやすく、湿気と結露が重なる冬場などには、カビの発生リスクを高める原因にもなります。
皮脂や油汚れを防ぐには、普段からサッシに触れる手を清潔に保つこと、また窓拭き用のアルコールを使った軽い拭き掃除を定期的に行うことが有効です。
カビ
窓サッシは結露や雨水などの湿気が溜まりやすく、カビの発生場所になりやすいため注意が必要です。
特に冬場や梅雨の時期は、外気との温度差によってサッシ内に結露水が発生しやすく、湿った環境が長く続くことで黒カビが生えやすくなります。
カビは目に見える部分だけでなく、サッシの溝や角、奥まった部分にも繁殖しやすく、放置すると掃除だけでは取り切れないことも少なくありません。
アレルギー症状や喘息などの健康被害を引き起こす場合もあるため、特に子どもや高齢者がいる家庭では注意しなければなりません。
カビの発生を防ぐためには、サッシを乾燥させることが効果的で、結露を見つけたらこまめに拭き取ったり窓を開けて換気したりするなどの習慣が有効です。
さらに、カビ防止スプレーを使用することで、湿気の多い時期でもカビの繁殖を抑える効果が期待できます。
水アカ
窓サッシに付着する水アカは、雨や結露によって発生することが多く、水分が蒸発する際に水中のカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が残って白く固まったものです。
特にサッシの溝や角は水が溜まりやすいため、水アカがこびりつきやすい場所となります。
放置すると硬化してしまい、通常の水拭きでは落としにくくなる点が特徴です。
水アカを防ぐには、雨のあとや結露が発生した際にこまめに乾拭きや水拭きを行うことが有効です。
また、重曹やクエン酸を用いて掃除すると水アカを柔らかくして落としやすくなるため、日常の掃除に取り入れるのがおすすめです。
窓サッシの掃除に必要なアイテムは?
窓サッシを効率よく掃除するには、次のようなアイテムを揃えておくと便利です。
窓サッシ掃除に必要なアイテム
・ブラシ
・掃除機
・メラミンスポンジ
・雑巾
まず、ブラシはサッシの溝や角に溜まった土埃や細かいゴミをかき出すために使います。
市販のサッシ用ブラシのほか、使い古しの歯ブラシでも代用可能で、隙間に届く小さめのブラシがあると作業がしやすくなります。
掃除機はブラシで浮かせたホコリやゴミを吸い取るのに役立ち、ノズルや隙間用のアタッチメントがあると奥まった部分もきれいにできます。
最後に雑巾は、表面の汚れや水分を拭き取ってサッシを清潔に保つために必要で、キッチンペーパーで代用しても構いません。
これらの道具を揃えておくことで、日常的な掃除から年に数回程度の入念な掃除まで、効率よく作業を進められます。
基本的に洗剤は不要
窓サッシを掃除する際は、基本的に洗剤を使わず水だけでも十分です。
なぜなら、窓サッシに付着する汚れは洗剤を使用しなくても落とせるものが多いためです。
汚れを楽に落としたいからといって、塩素系漂白剤のような強力な洗剤を使用すると、サッシ表面の変色や腐食を引き起こすおそれがあるため避けましょう。
また、スプレー式の洗剤を使う場合、液がサッシの隙間や周囲の壁、ベランダなどに飛び散りやすく、拭き取りが不十分であれば汚れが再付着する可能性があります。
実際には、窓サッシに付着する土埃やホコリ、花粉などの汚れは、洗剤を使わなくても水で湿らせたブラシや雑巾で十分に除去が可能です。
日常的な掃除であれば、水で湿らせた雑巾やスポンジを使い、こまめに拭き取るだけで清潔な状態を保てます。
年に数回程度の入念な掃除の際も、水だけでほとんどの汚れを落とせるため、基本的には洗剤を使う必要はほとんどありません。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!【簡単】窓サッシの掃除方法
「簡単に窓サッシの掃除を済ませたい」という方は、次の手順の掃除を月に1回程度を目安に行ってみてください。
窓サッシの簡単な掃除方法
①大まかな汚れをブラシで掃く
②汚れやゴミを掃除機で吸い取る
③メラミンスポンジでサッシを水拭きする
④掃除した部分の水分をしっかりと拭き取る
①大まかな汚れをブラシで掃く
窓サッシの掃除は、まずは大まかな汚れを取り除くことから始めるのが基本です。
サッシ用ブラシや古い歯ブラシを用意して、サッシの溝や角に溜まった砂や土埃、髪の毛などを軽く掃いて集めます。
特に窓の下部や角の隅には、外からの砂や室内のホコリが集まりやすく、放置するとこびりついてしまいます。
掃く際は力を入れすぎず、ブラシの毛先で丁寧にホコリを集めることがポイントです。
また、ブラシで掃く方向を一定にすると、汚れを中央や取りやすい位置にまとめられて、掃除をスムーズに進められます。
外側と内側の両方の溝に汚れがある場合は、内側から順番に掃くと効率がよく、外側に飛び散りにくくなります。
②汚れやゴミを掃除機で吸い取る
ブラシで大まかな汚れを集めたら、次は掃除機で細かいホコリや砂、髪の毛をしっかりと吸い取ります。
サッシの溝は狭く、通常の掃除機のヘッドでは吸引しにくいため、付属の細口ノズルや隙間用アタッチメントを使用すると効率的です。
ハンディタイプの掃除機があれば、手軽に狭い部分まで届いて作業効率がさらに向上します。
また、外側の溝にも砂や土埃が溜まりやすいため、外側から吸い取りつつ内側の溝も順番に掃除すると均一にきれいにすることが可能です。
掃除機をかける際は、吸引口をサッシに押し当てすぎないように注意して、ゴミを吸い込む感覚を確認しながら作業を進めましょう。
③メラミンスポンジでサッシを水拭きする
掃除機でホコリや砂を吸い取ったあとは、水で濡らして固く絞ったメラミンスポンジを使ってサッシの溝やフレームを丁寧に拭きましょう。
メラミンスポンジは細かな繊維構造となっていて、目に見えにくいこびりついた汚れや皮脂、油分をかき出す効果が期待できます。
あらかじめサッシの幅に合わせてカットしておくと、狭い溝や角の奥までスムーズに掃除できるため作業効率が上がります。
また、サッシ全体に水分が残ると汚れが再付着しやすくなるため、スポンジは固く絞るようにしましょう。
汚れが落ちにくい場合は、水を少量流しながらスポンジで拭き取って、細かな部分も丁寧に対応しましょう。
メラミンスポンジによって、ブラシや掃除機だけでは取りきれなかった汚れを効率よく除去でき、次の乾拭きの工程が格段に楽になります。
④掃除した部分の水分をしっかりと拭き取る
窓サッシを水拭きしたは、残った水分をしっかりと拭き取ることが重要です。
水分が残ったままになると、隙間部分に水アカができやすくなり、汚れの再付着やカビの発生につながります。
乾いた雑巾やキッチンペーパーを用意して、溝やフレームのすみずみまで丁寧に拭き上げましょう。
拭き取りは、一方向だけではなく溝に沿って縦横に動かすことで、残りやすい少量の水滴も取り除けます。
また、雑巾をこまめに絞ることも大切で、湿ったままの雑巾を使い続けると汚れや雑菌を広げてしまう原因になるため注意しましょう。
水分を完全に拭き取ることでサッシ表面が乾燥し、光沢感が戻るほか掃除直後から見た目の美しさが長持ちします。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!窓サッシにカビが生えた場合の掃除方法
特に結露が発生しやすい時期は、窓サッシにカビが生えることがあります。
頑固な壁は水拭きだけで落とすのは難しいため、重曹とクエン酸を活用して根本から取り除きましょう。
カビが生えた場合の掃除方法は、次のとおりです。
窓サッシのカビの掃除方法
①重曹とクエン酸を混ぜて、汚れが気になる部分に振りかける
②少量の水をかける
③発泡してから約30分放置する
④汚れをしっかりと拭き取る
⑤水分をしっかりと拭き取って乾燥させる
①重曹とクエン酸を混ぜて、汚れが気になる部分に振りかける
窓サッシにカビが発生した場合、まずは重曹とクエン酸を使った簡単な掃除方法から始めましょう。
重曹は弱アルカリ性で汚れや油分を浮かせる作用があり、クエン酸は酸性でミネラル汚れを分解する力があります。
2つを組み合わせることで、サッシの細かい溝や隅に入り込んだカビを効率よく除去することが可能です。
粉末を作る際には、混ぜすぎて粉が飛び散らないよう注意しましょう。
混ぜた粉はすぐに使用できる状態にしておき、掃除の直前にサッシのカビが生えた部分に振りかけます。
振りかける際には、カビの根元や角の部分にしっかりと粉を行き渡らせることがポイントです。
②少量の水をかける
次に、重曹とクエン酸を振りかけたカビ部分に、少量の水を加えます。
このときポイントになるのは、粉全体が湿る程度に水をかけることです。
大量の水を一度にかけると粉が流れ落ちてしまい、十分な発泡反応が起きずにカビへの効果が薄れてしまいます。
水が加わることで、重曹とクエン酸が化学反応を起こして泡が発生し、カビや汚れを浮かせてサッシの溝や角に入り込んだ汚れにも作用する仕組みです。
発泡中は粉末がしっかりとカビに密着している状態なので、拭き取る際に汚れやカビが剥がれやすくなります。
③発泡してから約30分放置する
泡が発生したら、約30分はそのまま放置するようにしましょう。
ある程度は放置することで、サッシの溝や角に入り込んだカビや汚れが泡になじみ、簡単に拭き取りやすくなります。
発泡後に急いで拭き取ってしまうと、カビが十分に浮かずに掃除後も残ってしまう可能性があります。
30分ほど待つことで、頑固なカビや汚れが緩んであとの拭き取り作業がスムーズになり、少ない力で効率よくきれいにすることができます。
④汚れをしっかりと拭き取る
発泡が終わったら、サッシについた重曹やクエン酸の粉と、浮いたカビ汚れをしっかり拭き取ります。
まず、乾いた雑巾やキッチンペーパーを用意し、泡と汚れを一緒に拭き取るようにします。
力任せにこすらず、汚れが浮いている間にやさしく拭き取ることが重要です。
拭き取る際には、重曹やクエン酸の粉が残らないよう丁寧に作業することが大切です。
粉が残ってしまうと、乾燥後に白い跡が残るため注意しましょう。
また、拭き取る流れとしては、サッシの奥から手前に向かって拭くと汚れを広げず効率的に拭き取れます。
⑤水分をしっかりと拭き取って乾燥させる
カビや汚れを拭き取ったあとは、サッシに残った水分を丁寧に拭き取ることが大切です。
水分が残ったまま放置すると、再びカビが繁殖したり金属部分にサビや腐食が発生したりする原因になります。
特に、サッシの端や隙間には水が残りやすいため、雑巾を折りたたんで細かく押さえるように拭くのがおすすめです。
また、拭き取りだけで完全に乾燥しきれない場合は、自然乾燥を併用するとよいでしょう。
風通しのよい場所で窓を開けておくと、短時間で乾燥させることが可能です。
窓ガラスの掃除方法
窓サッシの掃除中は約30分の待ち時間があるため、その間に窓ガラスもあわせて掃除するとよりきれいな環境を保てます。
窓ガラスは、次の手順で掃除しましょう。
窓ガラスの掃除方法
・ガラスクリーナーを含ませた雑巾でしっかりと拭く
・別の雑巾で窓ガラスを水拭きする
・乾いた布で乾拭きする
まず、ガラスクリーナーを含ませた雑巾でガラスの表面に付いた汚れや指紋を拭き取りましょう。
汚れがこびりついている場合も、ガラスクリーナーを使えばある程度は落とすことができます。
最後に乾いた布で乾拭きすることで、水滴の跡やムラを防ぎ、透明でピカピカの仕上げることが可能です。
窓ガラスを拭く際は、上から下へ順番に拭くか、左右にまっすぐ動かすと、効率よくムラなく掃除できます。
網戸の掃除方法
網戸は風通しをよくしてくれる一方で、ホコリや花粉、排気ガスなどの汚れが付着しやすい場所です。
放置すると黒ずみやベタつきが目立ち、室内の空気の清潔さにも影響を与えかねません。
そのため、窓サッシの掃除とあわせて、次の手順で掃除を行うのがおすすめです。
網戸の掃除方法
・ウェットタイプのシートをつけたフロアワイパーを用意する
・網戸を縦と横方向に分けて拭く
・外側も同じように拭く
・落ちたホコリやゴミを掃除機で吸い取る
フロアワイパーを使って網戸を上下左右から拭くことで、繊維に入り込んだ細かな汚れまでしっかりと取り除けます。
特に縦と横の両方向に拭くと、拭き残しが少なくなるため効果的です。
内側だけではなく、外側も同じように掃除するとより清潔に保てます。
窓サッシを掃除するおすすめの頻度は?
窓サッシは雨水や砂埃が溜まりやすく、放置すると黒ずみやカビの原因になります。
しかし、「窓サッシを毎日掃除するのは難しい」と考える方も多いでしょう。
おすすめの頻度は月に1回ほどの軽い掃除と、年2回程度の本格的な掃除です。
本格的な掃除に適しているのは、主に5月と11月です。
5月は花粉や黄砂の季節が終わり、梅雨前の湿気対策としても効果的な時期です。
11月は台風シーズンが過ぎたあとで、冬に向けて窓まわりを整えておくのに適しているといえます。
年末の大掃除として窓サッシの掃除を行う人も多いですが、12月は気温が低いため作業が大変になりやすく、窓を開けると室内が冷え込むので避ける方がよいでしょう。
窓サッシや窓ガラスの落としにくい汚れはプロに任せるのがおすすめ!
窓サッシや窓ガラスは、定期的に掃除していても水アカやカビ、こびりついた土埃などの頑固な汚れが残ってしまうことがあります。
特に、サッシの隙間やゴムパッキン部分は家庭用の道具では落としきれないケースも多く、無理にこすれば傷を付けてしまうおそれもあるでしょう。
もしこびりついた落としにくい汚れがある場合は、専門知識と高度な技術力を併せ持つプロのハウスクリーニング業者に依頼するのがおすすめです。
窓サッシの細かな部分だけではなく、窓ガラスや網戸まで丁寧に仕上げてもらえるため、全体的に見違えるほどきれいな状態になります。
また、プロに依頼することで時間や労力を大幅に節約できる点も大きな魅力です。
さらに、ハウスクリーニングは窓周りだけではなく、キッチンや浴室、エアコンなどの自宅全体の掃除にも対応しているため、年末や季節の節目にまとめて依頼するのもおすすめです。
とくに引っ越し前後や大掃除の時期には、効率よく家全体をリフレッシュできるサービスとして重宝されています。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!【初心者向け】ハウスクリーニング業者を選ぶ際のポイント
ハウスクリーニングを初めて利用する際、どの業者に依頼すればよいか迷う方は少なくありません。
料金の安さだけで決めてしまうと、思ったような仕上がりにならなかったり、追加費用が発生したりしてしまうケースもあるため、いくつかの基準を押さえて選ぶことが大切です。
特に初心者の方は、次のようなポイントを意識して業者を比較してみましょう。
ハウスクリーニング業者選びのポイント
・料金は適正価格か
・過去の実績が豊富で技術力があるか
・損害賠償保険に加入しているか
・口コミや評判がよいか
まず、依頼前には必ず見積もりを取り、作業内容と料金の内訳が明確に記載されているかを確認することが重要です。
ほかと比べて極端に料金が安い業者は、あとから高額な追加料金を請求されるリスクもあるため注意しましょう。
次に、過去の施工実績やビフォーアフター写真をチェックして、仕上がりのレベルや技術力を見極めましょう。
損害賠償保険に加入しているかどうかも必ず確認すべき重要なポイントで、掃除中の事故やトラブルで家具や壁を傷つけた場合でも、補償があれば安心して依頼できます。
最後に、口コミや評判も依頼する際の参考になります。
Googleマップや口コミサイト、SNSなどで評価を確認して、よい面と悪い面を比較して総合的に判断しましょう。
\お部屋まるごと掃除が最安10,000円~!/
近所のハウスクリーニング業者を調べる!窓サッシの掃除に関するよくある質問
窓サッシの掃除に高圧洗浄機を使うことは可能ですが、水圧が強すぎるとゴムパッキンや窓ガラスの隙間に水が入り込み、カビや劣化の原因になることがあります。使う場合は弱めの水圧に設定して、飛び散った汚れや水をしっかりと拭き取ることが大切です。不安な場合はプロの業者に任せるとよいでしょう。
窓サッシの掃除に必要な道具は、100均でも揃えられます。ブラシや隙間用スポンジ、メラミンスポンジ、ウェットシートなど、手軽に使えるアイテムが多数販売されています。特に細かい溝の掃除には小さなブラシが便利で、コストを抑えながら効率的に掃除できる点が魅力です。
風水の考え方では、窓ガラスや窓サッシをきれいに保つことはよい気を取り入れる行為とされており、運気の向上につながると考えられています。実際に、掃除によって室内に明るい光や新鮮な空気が入り込めば、気分がすっきりすることもあるでしょう。科学的根拠はありませんが、清潔な環境は暮らしを快適にして、気持ちのリフレッシュにもつながります。
窓サッシをこまめに掃除して清潔に保とう
窓サッシは砂埃や花粉、カビなどの汚れが溜まりやすい部分で、掃除を怠ると汚れが固着して簡単には落とせなくなってしまうほか、室内の空気環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、月に1回程度の軽い掃除を習慣化して、年に2回程度は本格的に掃除してきれいにするのがおすすめです。
特に湿気の多い梅雨や、砂埃が舞いやすい春先などは意識的にお手入れすると、清潔な状態を保ちやすくなります。
窓ガラスとあわせて清潔な状態を保てば、窓から入る光もより明るくなり、気持ちよく生活できるでしょう。
ただし、汚れが頑固にこびりついた場合や普段の掃除では手が届きにくい部分は、無理せずにプロの力を借りるのが安心です。
| 地域 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
| 中部 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
※本記事は、記事内で紹介している商品やサービス等について何らかの事項を保証するものではなく、いかなる組織や個人の意見を代表するものでもありません。記事内で紹介している商品やサービスについての詳細につきましては、当該商品やサービスの公式サイト等よりご確認いただきますようお願いいたします。
※記事内で紹介している商品の代金やサービスの代価等の額は一例であり、実際の金額とは異なる場合がございます。
※記事の内容は、記事の執筆ないし更新時点のものであり、現在の情報と異なる場合がございます。
\ハウスクリーニング探すなら「おうちにプロ」/
ハウスクリーニングを依頼する










